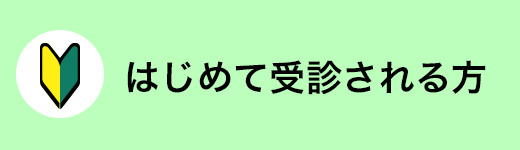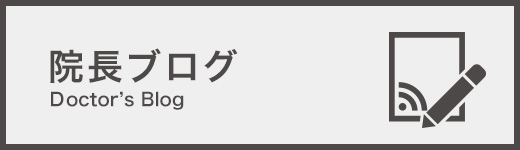鼻のトラブルの診断・治療
鼻 ― 呼吸と嗅覚を支える重要な臓器
鼻は単なる「空気の通り道」ではなく、吸い込んだ空気を温め・加湿し・浄化する機能、においを感じ取る嗅覚機能、さらには発声の共鳴にも関わる重要な器官です。
鼻の粘膜や副鼻腔に炎症が起こると、鼻づまり・鼻水・頭重感・嗅覚低下などさまざまな症状が現れ、睡眠の質や集中力にも影響を与えることがあります。鼻は空気の通り道であり、外気を温め・湿らせ・ほこりを取り除く働きを持っています。また、においを感じたり、声の響きにも関係するなど、生活に欠かせない器官です。
副鼻腔炎(蓄膿症)
鼻の周囲には「副鼻腔」と呼ばれる空洞が左右に4つずつあります。風邪やアレルギー性鼻炎などをきっかけにここに炎症が生じ細菌・真菌・ウイルス等が感染すると、膿や粘り気の強い鼻汁等がたまってしまいます。
急性の場合は風邪のあとに黄色い鼻水や鼻づまり、頭痛、頬の痛みが現れます。数か月以上症状が続くと「慢性副鼻腔炎」と呼ばれ、嗅覚の低下や後鼻漏(のどに鼻水が流れる)、咳が続くといった症状を伴うこともあります。
抗菌薬や副鼻腔洗浄(当院では副鼻腔自然孔からの洗浄を行っています)などの保存的治療で改善することが多いのですが、難治性の場合には手術(内視鏡下手術)を行うこともあります。
アレルギー性鼻炎
アレルギー性鼻炎は、特定の物質(アレルゲン)に対して過度に体の免疫反応が生じる疾患です。代表的な原因はスギやヒノキなどの花粉、ダニ、ハウスダスト、ペットの毛などです。
症状は、くしゃみ・透明な鼻水・鼻づまりを中心に、目のかゆみや涙目を伴うこともあります。重症化すると集中力の低下や睡眠障害を引き起こし、日常生活に影響することもあります。
治療は抗ヒスタミン薬・抗ロイコトリエン薬などの内服薬、点鼻ステロイド薬、環境整備が基本です。
また、アレルゲンに対して体の反応を徐々に慣らしていく「舌下免疫療法」は、根本的な改善が期待できる治療法として近年注目されています。
当院でも適応を確認のうえ、舌下免疫療法を含めた総合的な治療を行っています。
放置すると副鼻腔炎に移行することもありますので、早めに当院にご相談ください。
嗅覚障害
嗅覚障害とは、においを感じにくい(嗅覚低下)または全く感じない(嗅覚脱失)状態です。
原因は多岐にわたり、
-
風邪や副鼻腔炎などによる鼻粘膜の腫れ(気導性嗅覚障害)、鼻粘膜の変化
-
ウイルス感染や頭部外傷による嗅神経の障害(神経性嗅覚障害)
-
加齢や薬の副作用、神経変性疾患などによるもの等が挙げられます。
-
近年は、新型コロナウイルス感染後の嗅覚低下が注目されています。
診断には、においの定量検査(嗅覚検査)や内視鏡検査、CTなどを用いてその程度・原因を明らかにします。
治療は、ビタミン剤、ステロイド点鼻、漢方薬、「嗅覚リハビリ」と呼ばれる嗅覚刺激訓練などが中心となります。
発症から時間が経過するとさらに回復が難しくなることが多いので、早期の受診・治療が大切です。
好酸球性副鼻腔炎
好酸球性副鼻腔炎は、アレルギー体質や気管支喘息などに関連して起こるタイプの炎症性疾患です。
白血球の一種である「好酸球」が鼻や副鼻腔に集まり、強い炎症を引き起こすことで、粘り気の強い鼻汁や頑固な鼻づまり、嗅覚障害(においがわからない)などの症状を起こします。
鼻の中にポリープ(鼻茸)ができやすく、手術でいったん改善しても再発しやすい傾向があります。
治療は、ステロイド薬や抗ロイコトリエン薬などの薬物療法、必要に応じた内視鏡手術、近年では炎症を抑える「生物学的製剤(抗体製剤)」も選択肢となっています。
病気の特性を理解し、定期的な通院と長期的な管理を行う事が大切です。