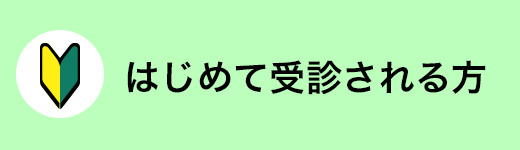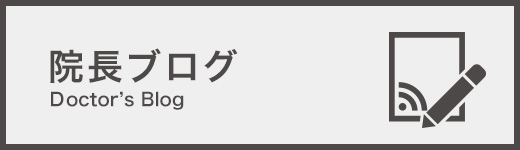のどのトラブルの診断・治療
咽喉頭(いんこうとう)は、のどの奥から声帯にかけての部分を指し、呼吸・嚥下(のみこみ)・発声に関わる大切な器官です。
この部位には、風邪や感染による急性咽頭炎・扁桃炎、急性喉頭炎、声の使いすぎによる声帯炎・声帯ポリープ、逆流性食道炎による喉頭肉芽腫、のどの違和感や異物感を訴える咽喉頭神経症(咽喉頭異常感症)など、さまざまな病気がみられます。
また、高齢者では嚥下障害(のみこみの障害)が問題となり、誤嚥性肺炎、長く続く咳の原因になることもあります。
診断には、耳鼻咽喉科で行う内視鏡検査が有用です。のどの奥まで直接観察することで、声帯の動きや炎症の有無を確認できます。
のどの痛みや違和感、声のかすれ、飲み込みにくさが続く場合は、早めの受診をおすすめします。
急性咽頭炎や急性扁桃炎などの主要な症状のひとつで、風邪の場合も喉に炎症を起こしやすく、時に痛みを感じることがあります。
扁桃炎
扁桃炎は、のどにある扁桃(口蓋扁桃)に細菌やウイルスが感染して炎症を起こす病気です。
風邪のあとに発症することが多く、のどの強い痛み、発熱、飲み込みにくさが主な症状です。重い場合には首のリンパ節の腫れや全身のだるさを伴うこともあります。
急性扁桃炎は、抗菌薬や消炎鎮痛薬で多くが改善しますが、再発を繰り返す場合や扁桃周囲膿瘍を生じた場合は、手術(扁桃摘出)が必要になることもあります。
また、溶連菌感染による扁桃炎では、腎臓や心臓の合併症を防ぐため、医師の指示に従って治療をしっかり行うことが大切です。
扁桃周囲膿瘍
扁桃周囲膿瘍は、扁桃炎が悪化して扁桃のまわりに膿(うみ)がたまった状態です。
のどの激しい痛みが片側に強く出て、口が開きにくい(開口障害)、飲み込みの痛みや発熱、声のこもりなどを伴います。発熱を伴います。
重症になると、膿がのどの奥へ広がり、入院加療が必要になります。呼吸や嚥下に影響することもあるため、早期の治療が必要です。
治療は、抗菌薬の投与とともに、膿がたまっている場合には切開・排膿処置を行います。
再発を繰り返す方や、慢性的に扁桃炎を起こす方では、扁桃摘出術を検討することもあります。
のどの片側の強い痛み、口が開けにくい、高熱などの症状がある場合は、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診してください。
急性喉頭蓋炎
急性喉頭蓋炎は、のどの奥にある喉頭蓋(こうとうがい)という軟骨のふたが、細菌感染により急に腫れ上がる病気です。
主な症状は、高熱・強いのどの痛み・飲み込みにくさ・声のこもりで、進行すると呼吸が苦しくなることがあります。
特に成人では、風邪のような症状から短時間で悪化することがあり、救急対応が必要となる危険な疾患です。
診断は、耳鼻咽喉科での喉頭内視鏡検査によって行います。
治療は、入院下での抗菌薬やステロイド投与、必要に応じて点滴や吸入を行い、呼吸の確保を最優先とします。
のどの強い痛みで唾が飲み込みにくい、呼吸が苦しい、声が出しにくいといった症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
のどの痛みがひどくなくても喉頭蓋の腫れがひどい場合もありますので、いつもと違うのどの違和感があった場合は出来るだけ早くに耳鼻咽喉科を受診してください。
上咽頭炎(じょういんとうえん)
上咽頭炎は、鼻の奥とのどの境目(上咽頭)に炎症が起こる病気です。風邪や鼻炎、アレルギーなどがきっかけとなり、ウイルスや細菌によって粘膜が腫れたり、痛みや違和感を生じます。
主な症状は、のどの奥の違和感、後鼻漏(鼻水がのどに流れる感じ)、軽いのどの痛みや耳の詰まり感などです。
慢性的になると、「のどの奥に何か張り付いた感じが取れない」「咳払いが続く」と訴える方も多くみられます。
診断は、耳鼻咽喉科での内視鏡検査によって上咽頭の状態を直接確認することで行います。
治療は、抗菌薬や消炎薬の投与、必要に応じて上咽頭処置(塩化亜鉛などでの局所治療:EAT)を行い、症状の改善を図ります。
下咽頭・喉頭がん(かいんとう・こうとうがん)
下咽頭・喉頭がんは、のどの奥(下咽頭)から声帯を含む喉頭にかけて発生する悪性腫瘍です。
初期症状としては、声のかすれ(嗄声)、のどの違和感や痛み、飲み込みにくさなどがみられます。
進行すると、食べ物がつかえる感じや血の混じった痰・呼吸のしにくさ・体重減少が起こることもあります。
原因としては、喫煙や飲酒が大きく関係しており、長年の生活習慣がリスクになります。
診断は、耳鼻咽喉科での内視鏡検査や生検(組織検査)によって行います。
治療は、放射線治療・手術・抗がん薬治療を組み合わせ、進行度や声の温存の可否に応じて選択されます。
早期に発見できれば声を保ちながらの治療も可能な場合があるため、声のかすれやのどの違和感が続く際は早めの受診をおすすめします。
中咽頭がん(ちゅういんとうがん)
中咽頭がんは、口の奥からのどの入口(中咽頭)にできる悪性腫瘍です。
発生部位は、扁桃(へんとう)や舌の付け根、のどの側壁などで、初期には症状が少なく、のどの違和感や飲み込みにくさ、軽い痛み程度のこともあります。
進行すると、飲食時の強い痛み、耳への放散痛、首のしこり(リンパ節転移)がみられるようになります。
原因としては、喫煙や飲酒に加え、近年ではヒトパピローマウイルス(HPV)感染が関与するタイプも増えています。
診断は、耳鼻咽喉科での内視鏡検査や組織検査で行い、治療は放射線治療・手術・化学療法を組み合わせます。
早期発見であれば治療成績は良好です。のどの違和感が続く、首のしこりがある場合は、早めの受診をおすすめします。
上咽頭がん(じょういんとうがん)
上咽頭がんは、鼻の奥とのどの境目(上咽頭)にできる悪性腫瘍です。
この部位は普段見えにくいため、早期には自覚症状が少なく、耳の詰まり感や難聴、鼻づまり、鼻血、首のしこり(リンパ節の腫れ)などで気づかれることがあります。
原因としては、EBウイルス(Epstein-Barr virus)感染との関連が知られており、アジア圏では比較的多いがんです。
診断は、耳鼻咽喉科での内視鏡検査や画像検査、組織検査によって行います。
治療は、放射線治療と化学療法の併用が中心で、早期に発見できれば高い治療効果が期待できます。
首の腫れや耳の違和感、片側の鼻づまりなどが続く場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診してください。早期診断が予後の改善につながります。
頸部のしこり(首のはれ・腫瘤)
首に触れる「しこり」は、リンパ節の腫れ、唾液腺や甲状腺の病変、のどや鼻の炎症、腫瘍(良性・悪性)など、さまざまな原因で起こります。
風邪や扁桃炎のあとにみられる一時的なリンパ節の腫れは多くの場合自然に治りますが、2〜3週間たっても小さくならない場合や、徐々に大きくなる場合は注意が必要です。
悪性リンパ腫や、咽頭・喉頭・甲状腺などのがんが転移していることもあり、早期発見が重要です。
耳鼻咽喉科では、触診や超音波検査、内視鏡検査、必要に応じて細胞診(注射による検査)を行い、原因を調べます。
しこりが長引く、痛みがないのに大きくなるといった場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診してください。早期の診断と適切な治療が大切です。