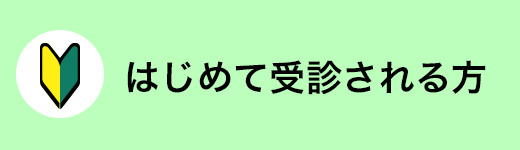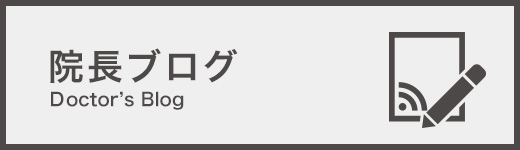睡眠時無呼吸症候群
わたしたちは、人生の約3分の1を「眠り」の中で過ごしています。
「朝すっきり起きられない」「日中眠くて集中できない」「いびきがひどい」――こうした症状の裏に、睡眠呼吸障害という重大な病気が隠れていることがあります。
睡眠呼吸障害とは睡眠中に呼吸が止まる、あるいは弱くなるなど睡眠の質が大きく低下する疾患です。体や脳が十分に休まらず、生活の質を大きく低下させます。高血圧、脳血管障害、心疾患、糖尿病、認知症との関連も深く、早期発見と適切な対処がとても重要です。その多くは耳鼻咽喉科の専門領域である上気道(鼻〜咽頭)の疾患と深く関係しておりますので、睡眠呼吸障害に対して耳鼻咽喉科医が関わることは理にかなっており、非常に重要です。
健康の三要素は食・運動・睡眠であると言われます。良質の睡眠がとれているか自覚症状のみでは判断が困難です。
睡眠時無呼吸症候群の検査(OCST・PSG)
睡眠中に呼吸が止まる、いびきが強い、日中に強い眠気がある場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われます。
診断のためには、睡眠中の呼吸状態を調べる検査が行われます。
まず行うのが簡易検査(OCST:在宅睡眠時呼吸モニター検査)で、自宅で装着できる小型装置を使い、睡眠中の呼吸の回数、酸素濃度、いびきなどを測定します。
結果により、より詳しい検査が必要な場合には、医療機関に1泊して行う精密検査(PSG:終夜睡眠ポリグラフ検査)を実施します。
PSGでは、脳波・心電図・筋電図なども同時に測定し、無呼吸の程度や眠りの質を正確に評価します。
検査結果をもとに、CPAP療法やマウスピース治療、生活指導など最適な治療法を検討します。
これらの検査とともに、耳鼻咽喉科では鼻づまり・扁桃や舌根の肥大・咽頭の形態など、気道の狭さの原因を直接観察できる内視鏡検査を行います。
鼻やのどの構造に問題がある場合、治療方針(CPAP・マウスピース・手術など)が大きく変わるため、睡眠時無呼吸の診断では耳鼻咽喉科での総合的な評価が非常に重要です。
いびきや無呼吸が気になる方は、まず耳鼻咽喉科にご相談ください。