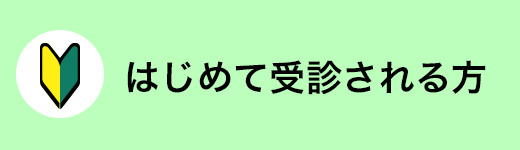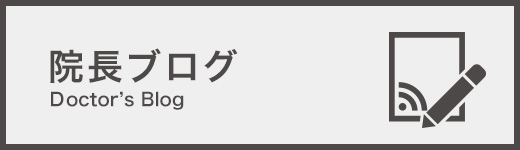めまいの診断・治療
耳鼻咽喉科で扱うめまい(末梢性めまい)とは
めまいは「体がふらつく」「周囲が回って見える」「まっすぐ歩けない」といった症状の総称で、原因は大きく「耳」「脳」「全身」に分けられます。
耳鼻咽喉科では、特に内耳(ないじ)や前庭神経の異常によるめまいを中心に診断・治療します。
耳の奥にある「三半規管」や「前庭」という器官は、体のバランスを保つセンサーです。ここに異常が起こるとめまいを感じます。
.
良性発作性頭位めまい症(BPPV)
寝返りをうつ、顔を上げる・下げる、起き上がるなど頭の位置を変えた時に生じるめまいが起こる病気です。
通常は数秒から1分以内でおさまります(時に長く遷延する事があります)。耳鳴や難聴を伴わないのが通常です。
原因は、内耳の「前庭」から外れた「耳石(じせき)」が、隣りにある「三半規管」に入り込むと頭を動かしたときの三半規管の信号が変化することで、体の動きと一致しない信号が脳に伝わるためです。
耳石を元の場所に戻すための浮遊耳石置換法が多くの場合有効です。
本疾患では眼振(末梢性眼振)という眼の動きがほとんどの症例で認められます(赤外線CCDカメラ下での眼振観察が特に有効です)。
眼振の向き・性状により行うべき浮遊耳石置換法を決定します。
正しい診断と正しい浮遊耳石置換法が重要です。当院では赤外線CCDカメラ下での眼振動画を毎回記録し、経過観察をおこないながら、眼振所見と病状に応じた治療を行っています。
耳鼻咽喉科領域のめまいのなかで最も多い病気です。
再発することも屡々あります。
メニエール病
めまい・耳鳴り・難聴・耳の詰まった感じを繰り返す病気です。めまいは回転性が多く、数十分から数時間続くことがあります。吐気を伴うこともあります。
内耳にある「内リンパ液」が過剰にたまり、内リンパ水腫と呼ばれる状態になることが関係していると考えられています。過労やストレス、睡眠不足などが誘因になることがあります。
治療は、内耳の循環を改善する薬や利尿薬の内服に加え、規則正しい生活と十分な休養、減塩などが大切です。
発作をくり返すうちに聴力が低下することもあるため、早期の受診と治療が重要です。
早期に耳鼻咽喉科へ受診する事をおすすめします。
前庭神経炎
突然、強い回転性のめまいが起こり、持続する病気です。吐き気や嘔吐を伴うこともありますが、耳鳴や難聴を伴わないのが特徴です。
多くの場合、風邪やウイルス感染のあとに発症します。耳から脳へ平衡感覚を伝える前庭神経の異常により発症すると考えられています。
急性期にはめまい止めや点滴で症状を和らげ安静を保ちますが、過度の運動制限は回復を妨げることがあり、いわゆる匙加減が大事となります。
急性期を過ぎると代償を促すための平衡リハビリを行うことで症状の改善を図っていきます。
回転性めまいは数日から1週間程度で徐々に軽快していきますが、ふらつきはしばらく残ります。
突然の強いめまいや歩行困難がある場合は、脳の病気との鑑別診断が重要です。
突発性難聴に伴うめまい
ある日突然、片方の耳の聞こえが悪くなり、同時にめまいを感じることがあります。これは「突発性難聴」にめまいを伴う疾患が最も考えられます。
原因ははっきりしていませんが、ウイルス感染や血流障害、ストレスなどが関係すると考えられています。
めまいを伴った突発性難聴は聞こえの回復の予後が悪い場合が多いので、出来るだけ早期の治療開始が重要です。
治療は、ステロイド薬の内服や点滴、内耳循環改善薬の投与などを行います。入院加療を勧める場合もあります。
めまいや耳鳴り、耳が詰まる感じ、急な聞こえの低下を感じた場合は、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診してください。
メニエール病の初発症状の可能性や、脳血管疾患の鑑別も必要となります。
PPPD(持続性知覚性姿勢誘発めまい)
PPPD(Persistent Postural-Perceptual Dizziness:持続性知覚性姿勢誘発めまい)は、ふらつきや揺れる感じが長く続くめまいの一種です。
明確な回転性のめまいではなく、「地面がふわふわする」「まっすぐ立つのが不安定」といった感覚が、立位や歩行、視覚刺激(人混み・画面)などで強くなるのが特徴です。
末梢性めまいの既往があり(BPPVやメニエール病など)回復の過程で視覚情報依存、体性感覚依存が過剰になっていることが関係していると考えられています。
治療は、めまいのリハビリ(平衡訓練)や抗不安薬・抗うつ薬の少量投与、心理的サポートなどを組み合わせて行います。
脳や全身が原因のめまい(中枢性・全身性)
-
脳梗塞・脳出血・小脳障害:歩行障害やろれつが回らないなどを伴う。
-
貧血・低血圧・自律神経失調:立ちくらみやふらつき型のめまい。
-
心因性めまい:ストレスや不安に関連して出現。
→ これらは耳鼻咽喉科でもスクリーニングを行い、必要に応じて神経内科・循環器内科へ紹介します。