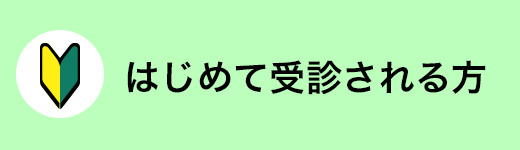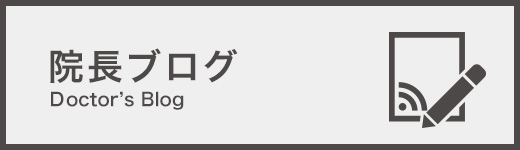嚥下障害
嚥下障害(飲み込みの障害)について
嚥下障害とは、食べ物や飲み物をうまく飲み込めない状態をいいます。むせる、のどに食べ物が残る感じがする、水分が気管に入って咳き込むなどが主な症状です。高齢者や脳卒中の後、神経や筋肉の病気、加齢によって起こりやすくなります。誤嚥性肺炎の原因となり、死に至る可能性もあります。飲み込みの異常を感じたら早めに受診して対策を取りましょう。軽度の嚥下障害の場合、訓練によって嚥下機能の改善が期待できますので、耳鼻咽喉科の受診をお勧めします。
耳鼻咽喉科の嚥下障害(えんげしょうがい)の診療
「食べ物や水が飲み込みにくい」「むせる」「痰がからむ」といった症状は、嚥下障害(えんげしょうがい)のサインです。
嚥下は、口・のど(咽頭)・食道が連携して行う繊細な動作で、耳鼻咽喉科はその中でも咽頭・喉頭・気道の専門科として、飲み込みの障害を詳しく診ることができます。
診断には、嚥下内視鏡検査(VE)を行い、実際に飲み込む様子を喉頭内視鏡で観察します。
食べ物や水がどの段階でつかえるのか、気管に入っていないかを直接確認できることが大きな特徴です。
必要に応じて頸部X線検査、嚥下造影検査(VF)を併用し、リハビリや食事形態の調整、内服治療、必要な場合は嚥下訓練や外科的治療を行います。
嚥下障害を放置すると、誤嚥性肺炎や低栄養につながります。
「最近むせやすい」「飲み込みにくい」と感じたら、早めに耳鼻咽喉科へご相談ください。